お歳暮とは、日頃お世話になっている感謝の気持ちをこめて、年末に贈るギフトです。誰に贈るべき、という決まりはありませんが、実は贈る相手によってマナーも異なります。この記事では、お歳暮を贈る相手や、予算、選ぶときに気をつけたいポイントをご紹介します。
教えてくれたのは、食事マナーや食文化に詳しい食の総合コンサルタントの小倉朋子さんです。

(食の総合コンサルタント・食輝塾主宰)
お歳暮は誰に贈ればいい?
お歳暮は、親戚、仲人、上司、取引先、主治医、お稽古事の先生、恩師など、日頃お世話になっている方に、感謝と「今後も末永くよろしくお願いします」という気持ちをこめて贈ります。また、日頃のねぎらいを込めて遠く離れた両親や、伴侶のご両親にも贈ります。
ただ、勤務先の上司や取引先などは、贈ったり受け取ったりすることを会社の規定で禁止している場合もあるので、注意が必要です。治療をしてくれた主治医なども同様に受け取らない場合があります。
お歳暮は、一度だけ贈るものではなく、毎年贈るものなので、あまり贈る相手を広げてしまうと大変ですね。吟味してある程度絞ってもいいでしょう。一度きり贈る相手には、お歳暮ではなく表書きは「御礼」としましょう。

お歳暮を贈る時期はいつ?
地域によって異なるのですが、お歳暮はおおむね12月上旬から中旬までに贈るようにしましょう。近年は、12月20日くらいまで構わないのですが、年末ぎりぎりでは、相手の方も多忙になります。
贈る時期を逃してしまったときは、年が明けてから1月7日の松の内までに届くようにします。その時、表書きは「お歳暮」ではなく「御年賀」で贈るとスマートです。
また、年が明けてからご縁をいただいた方や、諸事情で贈るのが松の内も過ぎてしまった場合、2月3日(立春の前日)までは、表書きを目下の人には「寒中御見舞い」、目上の人には「寒中御伺」として贈ります。
お歳暮の予算は?
3,000~1万円くらいが目安です。上司や仕事関連の方へは5,000円、親戚筋や知人は3,000円、その年に特に御世話になった方には5,000円~1万円くらいが相場です。仲人へも同様です。
また、別居をしているご両親には、贈る側が20歳以下であれば3,000円、社会人であれば5,000円くらいを目安にしてください。

お歳暮はマナー上、お返しは不要ですから、あまり高額ですと逆に先方に気を遣わせてしまうことにもなります。お返しはなくても御礼状は3日以内には出しましょう。親しい間であれば電話でも構いませんが、時期を逸しないことが大切です。単に「ありがとう」だけではなく、「どうおいしかった」ですとか「どう嬉しかったか」など具体的に伝えると贈った側も嬉しいですよね。
お礼の品をお返ししたい場合は、いただいた金額の半額を目途に選びましょう。お歳暮の金額は、贈る側と贈られる側の関係性だけでなく、経済動向や、収入や立場などにもよりますので、臨機応変に対応しましょう。
選ぶときに気を付けること
食べ物は家族で食べられれば残りにくいので喜ばれます。お子様のいるご家庭であれば大人も子供も食べられるお菓子、お酒好きな方にはお酒のつまみなど、相手の家族構成や趣向がわかっていればイメージして選びましょう。季節感も大切に。
生ものや冷凍、チルド商品を送る場合は特に、事前に送付状をお送りしておくのがエチケット。相手が旅行に行かれている間に届いてしまったらせっかくの感謝の気持ちが半減してしまいますよね。
毎年品物を変えるのが良いわけではありません。同じものを贈るのも覚えていただけるので良いでしょう。
少人数の家庭に多量の食品はご迷惑になるかもれません。また、アレルギーや持病を持っていることもあります。気になるならば、洗剤やタオルなど実用品や、お茶や海苔などの消耗品、保存が効く調味料など無難なものがおすすめです。

おとりよせネットでは、贈る相手やお好みのジャンルに合わせて、美味しいお歳暮・冬ギフトをご紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね。






























 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい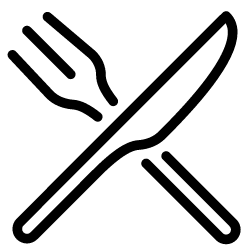 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



