多種多様な文化がある日本。特に”食”に関しては顕著で、ある地域は当たり前な事が、別の地域ではびっくり!ということも。そんな食にまつわる”地域の違い”にスポットを当ててご紹介します。今回は夏にぴったりな涼やかな食べ物、「ところてん」です。
奈良時代に登場した「ところてん」は超ベストセラー
まだ暑さが残る8月。見た目からも、食感も涼しいものが恋しくなります。日差しが強くて、食欲がイマイチという時におすすめなのが、ツルっとさっぱりとした『ところてん(心太)』。ところてんは、食物繊維が豊富で整腸効果があるので、この季節にぴったりです。

ゼリーや寒天のような歯ごたえのある感触が味わえるところてんですが、じつは材料は天草(テングサ)と呼ばれる海藻です。
漢字では「心太」と書くところてん。漢字の由来は諸説ありますが、最初は「こころぶと」と呼ばれていたために、その名の通り「心太」と表していたようです。「こころぶと」が次第に「こころてい」と呼ばれるようになり、さらに「ところてん」となったとか。古くは、奈良時代の書物にも「心天」という記載があるのが確認されており、千年以上前から食べ続けられている大ロングセラー商品といえます。歴史があるからこそ、数々の食文化が生まれ”地域差”に繋がっていくのかもしれません。
おかずにもデザートにもなるところてん。あなたは何をかける?
最近では、カロリーも低くヘルシーなためダイエット食としても注目を浴びているところてん。あなたは何をかけて食べますか?

関東を始めとする広い地域で親しまれている食べ方は、酢醤油や三杯酢をかけて食べる”おかず式”の食べ方。酢醤油には、好みでからしを付けたり、青のりを乗せてたりとより「おかずとしての満足度」を追及する場合も。酢醤油の酸味のあるしょっぱさが、ビールにも合いそう。小鉢で一品追加したいメニューです。
おかずに対して、デザートのように黒蜜を掛けて食べるのが関西地方。関東で見かける冷たいデザートとしての「葛切り」のように、ところてんに黒蜜やきなこをかけて和菓子のように食べます。ダイエット中だけれど、罪悪感がなく甘いものを食べたい人や、ちょっと小腹を満たしたい! というニーズにも合います。
さらにユニークな食べ方としては、高知県では、ところてんにカツオの出汁をかけるそう。さっぱりとした出汁の味は、暑い季節にも何皿でも食べてしまいそう。そして愛媛県では、薬味のショウガと一緒にめんつゆで、食べるそう。そうめんのようにチュルチュルと、ところてんをめんつゆで食べれば、食べ応えがあります。
ところてん自体には、あまり味はありませんがその分、先人たちは知恵を絞って美味しいトッピングを考えてくれたのかもしれませんね。
アレンジでバラエティ溢れる食べ方が可能なところてん
意外と奥が深いところてん。簡単に自宅でもアレンジができるので、一人暮らしの常備食としてもぴったりです。味付けがされていないところてんだったら、キムチや海苔をトッピングして辛さと歯ごたえを楽しんだり、アボガドやトマトというようなさっぱりとした野菜と合わせて、サラダ風に食べるのもおススメです。
掛けるものによって、いろいろな味の変化が楽しめるのが「ところてん」のよいところなのかもしれません。





























 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい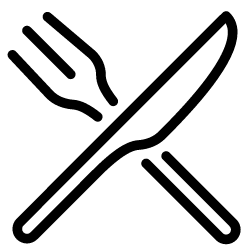 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



