
スイーツジャーナリスト
長年愛される「定番」スイーツ紹介の連載、第18回は、島根県の老舗「彩雲堂」より、江戸時代にこの地を治めた松江藩主が好んだと伝えられる「若草」をご紹介します。
松江藩主、松平不昧公が好んだ「若草」の由来とは?
島根県松江市は、松江城や宍道湖など、観光名所も多い風光明美な街です。江戸時代にこの地を治めたのは松江藩の松平家。中でも7代目藩主・松平治郷(はるさと)は、藩の中興の祖と称される人物。大名茶人としても知られ、「不昧(ふまい)」の号で、日本茶道史上に名を残しています。

そんな不昧公による茶道の手引き書『茶事十二ヶ月』の中に、この「若草」が、春の茶席の菓子として挙げられていました。不昧公が詠んだ「曇るぞよ 雨降らぬうちに摘みてこむ 栂尾の山の 春の若草」という歌に因み、名付けられたと言われます。しかし、時の流れと共に、その製法は失われてしまいました。
「彩雲堂」は1874年(明治7年)の創業。初代・山口善右衛門が、古老や茶人の伝承を元に研究を重ね、明治中期にこの「不昧公好み」の「若草」を蘇らせたそうです。
地元産もち米で作る求肥に、若草色のそぼろが春らしい装い
「若草」のベースは、四角い短冊形に切った求肥。奥出雲・仁多地方で穫れる良質のもち米を使用した、コシが強く弾力がありながら歯切れのよい食感が特徴です。

もち米を粉にする際、自社工場内の石臼で、水と一緒に少しずつ挽くという伝統的な製法を採用。それを熟練の職人が銅釜でじっくり練り上げ、求肥に仕上げます。
表面にまぶしたそぼろは、もち米を蒸して炒ってから粉末に挽き、さらにふるいにかけてきめ細かくした「寒梅粉」を若草色に染めたもの。1つ1つ手作業でまとわせています。
ほろほろした口当たりで、口に入れるとしっとり、少しサクサクとした食感に。中から現れる求肥の、もっちりした食感との対比も楽しめます。
3個入、6個入といった少量サイズから、24個入、30個入といったサイズまで揃うので、用途に応じて選ぶことが可能。常温で保存できて日保ちも長めなので、毎日少しずつ味わうのもいいですね。
江戸時代の製法を蘇らせた復刻版「若草」もあり
2018年には、松平不昧公の没後200年を迎え、復刻版の「不昧公 若草」が発売されました。ヨモギを用いた当時の製法記述を元に、ヨモギ粉末入りの寒梅粉をまぶしたものです。口にすると、春を感じさせる清々しい香りがふわりと広がります。

こちらは、本店の店頭での販売のみ、稀に催事の時などに並ぶことがある限定バージョン。かつて不昧公も、お茶席でこのようなお菓子を召し上がっていたのでしょうか。歴史のロマンを感じさせる一品です。
本店の2階には工芸菓子が展示されていて、四季折々の花鳥風月など、お菓子の素材で精巧に作られた作品が並びます。私も、念願かなって訪問した際には、松江に息づく菓子職人の技術の高さに感銘を受けました。

もちろん、お抹茶との相性は抜群。松江の歴史に思いを馳せながら召し上がっていただきたいお菓子です。






























 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい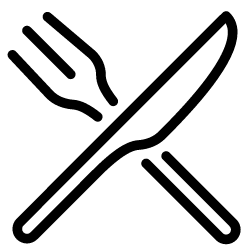 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



