日頃の感謝の気持ちを伝えるためのお中元。この贈り物に欠かせないが「のし(熨斗)」です。毎年のことだけれど、のしの選び方や書き方もいつも店員さんにお任せしているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「のしの意味は?」「書くときのペンはどれ?」「喪中の時はどうしたらいい?」など、のしについて知っておきたいルールやマナーについてご紹介します。
お中元の「のし」とは?
そもそも「のし」とは、その昔、不老長寿を意味する“鮑(あわび)”を乾燥させて伸ばし、縁起物として贈答品に添えていたことが始まりと言われています。“伸し鮑”が“熨斗鮑(のしあわび)”に変化し、現在まで風習として残っています。
現在では鮑は使われなくなり、贈答品には紙で作られたのしを品物の右上もしくは右側に付ける付けるか、のしが印刷されている“のし紙”を付けるなど、簡略的なものになっています。しかしのし紙は包装を省いた略式の贈答方法であり、場合によって使い分ける必要があります。
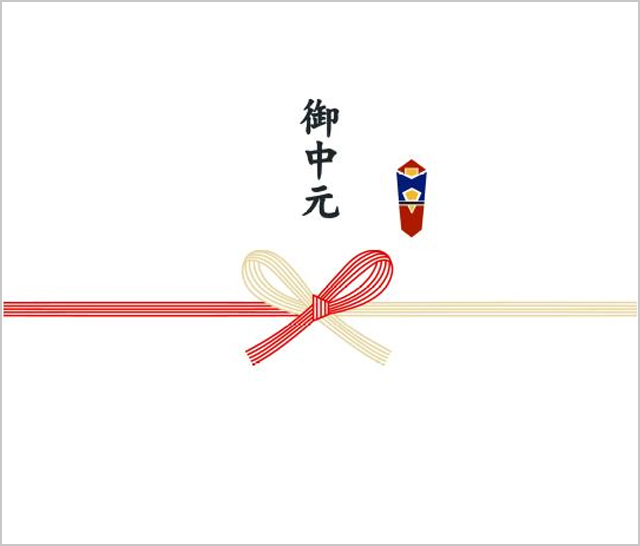
内のし
「内のし」は、品物に直接のし紙をかけてから包装紙で包みます。順序としては、【品物→のし紙→包装紙】となります。
品物に直接のし紙をかけるので、外側からはのし紙が見えません。また、のし紙が汚れたり、破れたりする心配もありません。
包装紙がなかった昔には、品物に直接のし紙をかけたものを風呂敷に包み、そのまま持参したそう。そういった意味では、この方法は昔から続く本来のやり方に近いとも言えます。
外のし
「外のし」は、品物を包装紙で包み、その上からのし紙をかけます。順序としては、【品物→包装紙→のし紙】となります。
包装紙の上からのし紙をかけるので、外側からのし紙が見えます。大勢の方から品物をいただくような場合、外のしだと表書きが見えるので、先様が誰から何を、どんな目的で贈られたのかが一目で分かります。
贈答品を人前で披露されることがある場合や直接先様へ手渡す場合は、のし紙が見えている外のしの形で渡すのがマナーです。
短冊
のし紙を使用しない場合は、「短冊」を使用することもあります。短冊は“短冊のし”とも言われ、略式されたのし紙の一種です。資源の無駄遣いをなくすために百貨店などで使用されるケースが多いです。
短冊のしを付ける場合は、品物の右上もしくは右側に付けるようにします。短冊のしは一般的な贈答用として失礼にあたることはありませんので、ご安心ください。
水引
慶事や弔事の贈り物などに使う「水引」は、古来中国からの輸入品に紅白の紐が結われていたことから、日本でも定着したと言われています。最近では紐を結ばずとも、かけ紙や袋に水引が印刷されているものを使用することも多くあります。
お中元には紅白の水引を使い、結び方は蝶結びにします。「紅白の水引」は、慶事全般に使用されます。また「蝶結び(花結び)」も“何度でも結び直せる”の意味から、お祝い事に用いられる結び方です。
表書き
のし紙には、贈り物の目的や贈り主の名前を書きます。これを“表書き”と言います。上段には大きく「御中元」もしくは「御礼」などと書き、水引を挟んだ下段には、上段よりもやや小さめで贈り主の名前を書きましょう。
表書きは、贈るシーズンによって異なります。お中元シーズン中の場合は上記の通りですが、過ぎてしまった場合~立秋までは「暑中御見舞」、立秋~処暑までは「残暑御見舞」として贈ります。目上の方へ贈る場合は、それぞれ「暑中御伺い」「残暑御伺い」とします。
名入れ
水引を挟んだ下段には、上段よりもやや小さめで贈り主の名前を書きます。これを“名入れ”と言います。
家族で贈る場合は、姓のみを記入するか、家長の姓名を書くようにします。会社などで連名という形で贈る場合は、役職が上の方から順に、中央→右→左へと名前を入れていきます。同等の立場で連名とする場合は、水引を中心にして左右に書きます。
連名の場合は、文字がのしや水引に掛からないようにしましょう。また、使用するペンは濃い色の筆ペンやサインペンを選びます。
お中元の「のし紙」の書き方をご紹介
個人名
個人名で贈る場合は、水引を挟んだ表書きの真下にフルネームで書きます。表書きよりもやや小さめの文字で書くようにしましょう。また、目下の方へ贈る場合は名字だけでも構いません。
夫婦の連名
夫婦の連名で贈る場合は、表書きの真下に夫のフルネームを書き、その左側に妻の名前のみを書くようにします。
連名
贈り主が複数いて連名とする場合、3名までとした場合と、4名以上とでは、書き方が異なってきます。
- 3名までの場合:役職や地位に従って順に、中央→右→左と書きます。同等の立場であれば、五十音順に書きます。
- 4名以上の場合:代表者の名前を表書きの真下に書き、その左側に「他一同」「有志一同」と書いて、他の方々の名前は中包みに記載します。
会社名
会社名を入れる場合は、表書きの真下に名前がくるように書き、その少し右に小さめに会社名を書くようにします。会社名に英数字が使われている場合は、カタカナ表記で書きましょう。会社名を入れる際には、全体の位置バランスをよく見て書くようにします。
代表者名
連名で4名以上となる場合は、代表者の名前を表書きの真下に書き、その左下に「他一同」もしくは「有志一同」と書きます。代表者以外の他の方々の名前は、中包みに記載します。
喪中の際は注意
お中元を贈る側、または贈られる側が喪中の場合は、のし紙はつけません。水引やのしのついていない無地の奉書紙や白短冊をつけて贈ります。もし贈る相手が喪中であることを知らずにのし紙を掛けてしまった場合は、電話でお詫びをしましょう。
「のし」のマナー
生モノにはのしを付けない
贈り物にのしを付けるのは基本的ですが、“生モノ”を贈る場合、のしは不要となります。お肉や魚介類など、また生モノのイメージ付きにくい鰹節なども、のしは付けません。
のしの由来である“伸し鮑”は、古来より不老長寿を意味する鮑を伸ばして干したものを贈答品に添えることで、「命を延ばす」という意味にも繋がりました。そのため、贈答品が生モノの場合、のしと合わせて二重の意味になってしまうため、のしを付けないのです。
黒以外のペンは使わないようにする
表書きも名前も本来であれば、毛筆で書くことが望ましいです。難しい場合は、筆ペンやフェルトペン、サインペンを使いましょう。ボールペンや鉛筆は避けてください。
また、お祝い事の文字は濃い黒で書くこととされています。色が薄かったり、かすれてしまっていると弔い事を表してしまうため、ご注意を。
公務員の方にはお中元は送らない
公務員や一部の民間企業では、お中元などのやり取りを禁止しているところもあります。これは、「利害関係者からお金や物品の贈与を受け取ってはならない」という決まりがあるためです。迷ったら、贈る前に相手に確認しておきましょう。
お中元を贈る際に気を付けるポイント
相手の好みに合わない物
相手の好みに合わない物は、贈らないように気をつけましょう。好みが分からなければ、まず好き嫌いが分かれる物は避けた方がベスト。珍味や缶詰、香味野菜を使ったものなど、味や匂いが特徴的なものは外します。
また、保存がきかない生鮮食品もできるだけ避けます。配送時に不在だったり、長期で家を開けている場合、贈り物が食べられなくなってしまうからです。どうしても贈りたい場合は、相手の都合などを確認してから贈るようにしましょう。
家族構成を無視した物
相手の家族構成をふまえて贈るのも喜ばれるでしょう。何人家族でどのようなライフスタイルなのか、想定して贈り物を選びます。
一人暮らしや核家族の場合、大量の物を贈られても困りもの。この場合は、レトルト食品や加工食品、小包装のお菓子など、少量で常温保存可能、なおかつ賞味期限が長いものがよいでしょう。
家族が大勢の場合は、量もそれなりに充実した物を選びます。また、洗剤などの日用品は、どのような家族構成の方でも助かります。
基本的に贈ってはいけない品物も存在する
相手の好みを考えるのも大切なことですが、贈り物にしてはいけないものもあります。代表的なものが下記になります。
- 履物、靴下や下着:踏みつける、みすぼらしいという意味になります
- 刃物類:縁を切るという意味になります
- 現金や金券:お金に困っているという意味になります
- 筆記用具や時計:勤勉奨励という意味になります
特に目上の方に贈る場合は、好き嫌いの考慮も大切ですが、「贈ってはいけない物」があることに重々注意して選ぶようにしましょう。
高価すぎる物
贈る物の相場は、一般的に3,000円〜5,000円と言われています。あまり高額な物を贈ると、相手の負担になるのでご注意を。特にお世話になっている目上の方にも、1万円を越えるものを贈るのは避けるべきです。
お中元は日頃の感謝の気持ちを伝えるための贈り物なので、相手に気持ちよく受け取ってもらえる程度に納めます。また、これは1回限りではなく、毎年のものですので、お互い無理なく続けられる金額にしましょう。
お中元は一度贈ったら毎年贈るもの
上記の通り、お中元は一度贈ったらおしまいという訳ではありません。一度贈ったら毎年贈り続けるのがマナーで、途中で止めることは失礼にあたります。
しかし、長い年月の中で、相互の環境が変化し、お付き合いも疎遠になっていくこともあります。季節の贈答品だけのやり取りだけになっていると感じるようであれば、贈るのを止めることも考えてもよいでしょう。本来、贈り物は日頃の感謝の気持ちを伝えるためのもの。それが虚礼だけのことになってしまったならば、止め時かもしれません。
おとりよせネットでは、松阪牛のハンバーグや老舗のそうめん、カラフルなゼリー、こしあんを使ったクッキーなど、お中元におすすめのお取り寄せグルメ&スイーツをご紹介中。ぜひ参考にしてみてくださいね。
お中元の包み方をご紹介
「通常」の包み方
お中元を贈る場合は、必ずのしを付けて贈ります。のしは、慶事全般に使用される「紅白の水引」を使い、結び方は何度でも結び直せるの意味を持つ「蝶結び(花結び)」を選びます。のしのかけ方は、内のし、外のし、どちらでも構いません。表書きと名前は必ず書きましょう。
「相手が喪中」の包み方
相手が喪中の場合でも、贈って差し支えはありません。贈る時期が忌明け後であれば、例年通りに。忌明け前に贈る時期が来た場合は、忌明け後の四十九日を過ぎてから、「暑中御見舞」もしくは「残暑御見舞」として贈ります。
のしも変わらず付けますが、紅白の水引と花結びではなく、無地の短冊か真っ白な奉書紙を使用し、地味な包装紙で包みます。故人や相手を偲ぶメッセージカードを添えて贈るのもよいでしょう。
「残暑見舞い」の包み方
「残暑見舞い」として贈る際も、のしは紅白の水引で「蝶結び(花結び)」を選びます。表書きには、目上の方に宛てる場合は「残暑御見舞」、目下の方に宛てる場合は「残暑御伺い」と書き、水引を挟んだ真下に名前を書きます。のしのかけ方は、内のし、外のし、どちらでも構いません。
「残暑見舞い+喪中」の包み方
喪中の方へ「残暑見舞い」として贈る際は、のしや水引は使用せず、無地の短冊か真っ白な奉書紙を使い、地味な包装紙で包みます。表書きは変わらず書きます。目上の方に宛てる場合は「残暑御見舞」、目下の方に宛てる場合は「残暑御伺い」と書き、水引を挟んだ真下に名前を書きましょう。
「のし」の書き方ひとつで関係性が変わってしまうことも
のしや掛紙はそれぞれに意味を持つため、選び方や書き方には細かなマナーがあります。せっかく相手のためにと選んだ贈り物が、マナーひとつで失礼にあたってしまうのは、とても残念なことです。正しい作法を守り、相手にも気持ちよく受け取ってもらえるようにしましょう。
大切な方とのコミュニケーションにはいろいろな方法がありますが、世代問わず相手との良好な関係を保つための一つの方法として、日本ならではお中元という習慣で良好な関係を作っていきましょう。
































 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい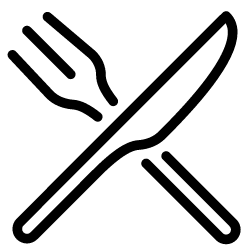 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



