あっという間に今年も残すところわずか。慌ただしい年末が過ぎれば、来たるは新年のお正月です。お正月と言えば、各々の家庭で振る舞われる「おせち料理」ですが、そこで使われている具材には、それぞれ意味や願いが込められていることをご存知でしたか? 今回は、そんな知っているようで実はあまり知らないおせち料理についてご紹介いたします♪
おせち料理の意味・由来とは?
毎年、お正月になると振る舞われる「おせち(御節)料理」ですが、そもそもおせち料理はお正月だけのものではありませんでした。元旦や五節句などの節日を祝うため、神様にお供えしていた“おせちく(御節供)”が、江戸時代頃になると庶民の間に広がり、一年のうちで一番大切にされていたお正月にいただく「おせち料理」へと変わっていったようです。

おせち料理に使う食材は、元々は収穫のご報告や感謝の意を込め、その土地で獲れたものをお供えしていたようですが、食文化が豊かになるにつれて、山海の幸を盛り込んだご馳走になっていきました。
また、お正月三が日は、かまどの神様にお休みいただくことが言われるようになり、今のような保存も効く食材や調理法となっていきました。
各おせち料理(具材)の意味
おせち料理の具材は、それぞれの地域や家庭でも異なりますが、その種類は20〜30ほどあると言われています。具材にはそれぞれ意味や願いが込められており、一年の始まりであるお正月に、その意味や願いとともにいただく大切な料理となっています。

黒豆
まめに働き、まめに健康に暮らせますようにという願いが込められています。また、あえてシワが出るように煮て、シワができるほどの長寿を願うという意味もあります。
数の子
多くの卵が付いている数の子は、子孫繁栄や子宝に恵まれることを願う食材です。また、ニシンの子なので「二親健在」という意味も含まれています。
海老
海老はその丸く曲がっている姿から、腰が曲がるまで長生きできるよう願いが込められています。また、身が赤く美しいことから縁起物や魔除けの意味もあります。
れんこん
穴があいていることから、将来の見通しがきくようにという祈りが込められています。また、極楽浄土の池には蓮の花が咲くことから、穢れのないことを現しています。
里芋
里芋は子芋がたくさん付くことから子孫繁栄を表しています。
ごぼう
ごぼうは根を土中にしっかり張ることから、家族の土台がしっかりすることや家業が土地に根付くことの願いが込められています。
栗きんとん
栗は「勝ち栗」と呼ばれる縁起ものです。「金団」と書き、黄金色で縁起がよく、金銀財宝を連想させることから蓄財に繋がるとされています。
伊達巻
「伊達」とは華やかという意味があり、昔の伊達者(しゃれ者)たちの着物に似ていたので、伊達巻と呼ばれるようになったと言われています。巻き物が書物や掛軸に通じることから、知識や文化の発達への願いが込まれています。
錦卵
卵の黄身と白身の2色が、金と銀に例えられており、“2色”を「錦」と語呂合わせしているとも言われています。ハレの日の食材にぴったりです。
筑前煮
様々な具材を一緒に煮ていることから、家族一緒に仲良く結ばれることの願いが込められています。具材は縁起物が選ばれることが多いです。
鯛
鯛は「めでたい」の語呂にかけられています。また、姿も味もよいので、江戸時代から「人は武士、柱は檜(ひ)の木、魚は鯛」と言われ、めでたい魚として祝膳には欠かせないものとなっています。
紅白なます
紅白でめでたく、祝いの水引にも通じています。また、根菜のように根を張るようにとの願いが込められています。
田作り
田作りで使うイワシが畑の肥料だったことから「田作り」「五万米」(ごまめ)と呼ばれ、豊作祈願の料理とされています。
お取り寄せ・通販できるおせち料理
京都から届く本格的なおせちなど、お取り寄せ・通販したい、人気のおせち料理をご紹介します。






























 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい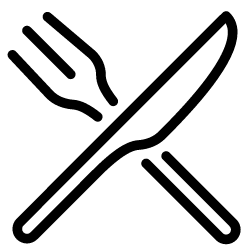 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



