多種多様な文化がある日本。特に”食”に関しては顕著で、ある地域は当たり前な事が、別の地域ではびっくり!ということも。そんな食にまつわる”地域の違い”にスポットを当ててご紹介します。今回は、同じ名前でありながら実は関東と関西でまったく違う和菓子「くず餅」です。
くず餅の食感はぷるん? それともモチモチ?
「くず餅」と聞いて、あなたはどんなものが浮かびましたか? ぷるんとした独特の食感で透明のくず餅でしょうか。あるいは、おでんのこんにゃくのように、三角形や四角形に切った白っぽいお餅のようなものでしょうか。どちらも「くず餅」と呼ばれているのに、味から見た目までまるで違う商品なのは、いったいどうしてなのでしょうか。
透明でぷるんとした食感のくず餅は、関西で見かけるもので、葛粉から作られています。とろみのある透明なくず餅は、葛粉に砂糖と水を加え、火にかけて練ったもの。この手間暇かけたとろみは、まさに和菓子ならではのほのかな甘さが漂います。関西風のくず餅に使われている葛粉の原料となるくずは、マメ科の多年草。くず餅以外にも、葛湯や葛切りなど様々な料理に使われています。

和菓子というよりも、おかずのようなボリューム感のあるお餅のようなくず餅は、関東で見かけるもの。小麦を乳酸菌で発酵させたでんぷんで作られています。小麦の配合や発酵期間などの違いから、同じ関東風のくず餅でも、異なった食感を持つくず餅が生まれているようです。小麦を主原料としているため、関東のくず餅は白く濁っています。関西風よりも見た目は餅に近いかもしれません。関西風くず餅と区別するために、久寿餅と表記していた時代もあったようです。

さらに変わり種と言えば、沖縄のくず餅。芋のでんぷんと言われている芋くずから作られています。黒みつは掛けずに、直接餅に黒糖が練りこまれた沖縄風くず餅は、関西風のツルっとした食感とはまた違った、モチっとした噛み応えが特徴です。
同じ名前なのに、見た目も食材も異なる「くず餅」。最近では、おとりよせなどで色々な種類のくず餅が購入できるので、食べ比べてみては?
胃腸に優しく低カロリーのくず餅は、ヘルシー食
小麦を乳酸菌で発酵させて作られた関東風のくず餅は、実は和菓子唯一の発酵食品。植物性乳酸菌が沢山含まれているため、お腹に優しく低カロリー。ほんのりとした甘さの黒糖ときな粉は、クリームたっぷりの洋菓子よりも罪悪感が少ないかもしれません。弾力のあるくず餅をゆっくり噛めば、満腹中枢も満たされるかもしれません。
また葛粉には、身体を温める効果や整腸作用があると言われています。葛粉を使った関西風のくず餅は、風邪で食欲が低下している時にも、のど越しもまろやかなため食べやすいのでお勧めです。
その涼感のある食べ心地から、夏の和菓子としてとらえがちなくず餅ですが、これから寒くなる季節にも、意外と万能フードと言えそうです。
最後にくず餅を美味しく食べるテクニックを。最初に黒みつを掛けた後にきな粉を掛ける方が、黒みつがくず餅に絡みあい、より一層、風味が増しますよ。ぜひ試してみてくださいね。






























 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい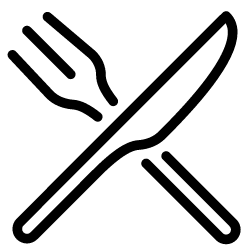 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



