毎月3日間だけ販売されるという、特別などら焼きをご存知でしょうか。しかも見た目は、一般的に知られているような円盤形ではなく、円柱状。今回は、江戸時代から長く愛される、他にはないどら焼きをご紹介します。
笹屋伊織の「どら焼」が円柱状になっている理由
享保元年(1716年)創業の笹屋伊織は、京都にある和菓子の老舗。その笹屋伊織が作る「どら焼」は、まずその見た目が他のどら焼きとは大きく異なります。

そう、竹の皮に包まれた円柱状になっていて、それを竹の皮ごと輪切りにしていただくのです。円柱状になっているのには理由があります。
江戸時代末期、京都の東寺(とうじ)のお坊さんから副食になる菓子を作って欲しいとの依頼を受けたのが、5代目当主の笹屋伊兵衛。そこでお寺でも作ることができるようにと鉄板の代わりに使ったのが銅鑼でした。
熱した銅鑼に薄く生地を引き、そこに棒状にしたこしあんを乗せてくるくると巻き込んで、細長い円柱状のどら焼きを作ります。それを竹の皮で包み込んで完成したのが、笹屋伊織の「どら焼」です。

竹の皮に包まれているため、どら焼きからはふわりと竹の香りが漂います。そのせいか、どこか懐かしさすら覚えます。バウムクーヘンのような層になった皮は、一般的などら焼きとはまったく違うもっちりとした食感。その皮に包まれたこしあんは、一見とても甘そうに見えるのですが程よい甘さ。なめらかな食感で、すっきりとした後味です。しっかり噛んで食べることもあってか、小さく切って食べても満足感があります。
笹屋伊織の「どら焼」が月に3日間しか販売されない理由
笹屋伊織の「どら焼」の美味しさはたちまち評判となり、お坊さんだけではなく街の人々もこぞって買うようになったそうなのですが、手間ひまをかけるため、大量に作ることはできなかったそうです。そこで、東寺ご参拝のお土産として、弘法大師の月命日である21日だけの限定販売としたそうです(ちなみに東寺は、「お大師様の寺」とも呼ばれる、弘法大師ゆかりのお寺です)。
いまでは販売期間を3日間に延ばし、店頭では毎月20日21日22日に販売、オンラインショップでは毎月15日に申し込みを締め切り、毎月20日21日22日に到着できるよう、予約販売しています(地域によっては、到着日がずれることもあります)。

江戸時代からずっと変わらぬ製法で作られており、その詳しい作り方は代々の当主だけが知る秘伝とのこと。その見た目、味わい、歴史など、手土産やギフトにすればきっと喜んでもらえると思います。





























 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい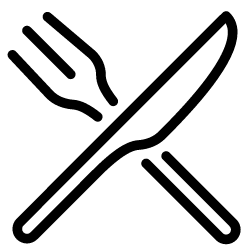 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



