長く愛され続ける「老舗の定番」をご紹介する連載。第三回目は、江戸時代の創業以来、200年以上の歴史を持つ老舗の看板商品「元祖くず餅」です。
「船橋」の屋号を持つ、亀戸の老舗和菓子店
東京の下町、亀戸に本店を構える和菓子店「船橋屋」。創業は江戸の文化二年(1805年)。屋号は、初代の勘助氏が現在の千葉県の「船橋」出身だったことから。当時、この地域は良質な小麦の産地でした。

勘助は、上京後、湯で練った小麦澱粉をせいろで蒸した餅に、黒蜜きな粉をかけて、「亀戸天神」の参拝客に販売しました。それが評判となり、「くず餅」と名づけられ、江戸の名物の一つになったそうです。
「葛餅」ではなく「くず餅」、その製法は?
このように「船橋屋」の「元祖くず餅」は、葛粉を使った「葛餅」とは異なるもの。さらに、小麦澱粉を450日もかけて乳酸発酵させて蒸し上げるという、とても珍しい製法です。これにより、適度な弾力や、しなやかな歯触りが引き出されます。今回、特別に本店併設の工場見学をさせていただきました。

発酵した小麦澱粉を溶かした水に湯を足してとろみをつけ、せいろに布を敷いて木製の升に流し、トンネル状の蒸し器の中を通します。工場の中はかなりの熱気!真夏は、さぞ大変なことでしょう……

せいろから出た餅は、熟練の職人さんが、手に水をちょっとつけて触り、弾力などを確かめます。熱々なので、一瞬の技ですが、季節や気候による僅かな差も見極め、必要に応じ蒸す温度や生地の濃度調整なども行います。この後、すのこの上に移し、粗熱を取ってから裁断機でカットし、包装して完成です。
日保ちの短さに価値がある!お勧めの食べ方
発酵させた小麦澱粉は、独特の酸味のある香りですが、水に溶かし、洗って沈殿させて、酸味や雑味を除きます。そのため、完成した「元祖くず餅」に酸味を感じる訳ではありません。でも、どこかパンを思わせるような、ほのかな発酵の残り香も感じられます。

この「元祖くず餅」、実は日保ちが短く、オンライン購入すると、消費期限は到着の翌日まで。少々ハードルが高いですが、昔は関東外に持ち出すのも困難だった東京名物が、全国で楽しめるようになったというのは、凄いことですね。
24切入りが1-1.5名用とのこと。量が多そうですが、食べ始めると、つい止まらなくなってしまいます。お試しサイズの6切入りカップもあり、人数に応じて60切入りまで揃います。
黒蜜ときな粉もたっぷり、存分にかけても余るほど。黒蜜の容器が舟形なのも、店名に因んだ遊び心ですね。冷蔵庫に入れると少し硬くなるので、常温でいただくのがお勧めだそうです。

本店の喫茶室に掲げられた看板の店名は、船橋屋の黒蜜のファンだったという作家の吉川英治氏の筆。沖縄産の黒糖をベースにしたブレンドした秘伝の味。濃厚な味と香りで、それ自体には甘みのない、さっぱりした餅と相性抜群!香ばしいきな粉も、味わいを引き立ててくれます。
江戸時代の知恵が生きた、体にもやさしい乳酸菌発酵食品「元祖くず餅」。食べて元気になれそうですね。

スイーツジャーナリスト






























 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい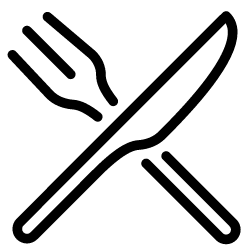 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



