大晦日に食べる「年越しそば」。諸説あるといわれる意味や由来、歴史について説明。1年の締めくくりにぴったりな絶品年越しそばもご紹介します。
年越しそばの意味・由来とは
大晦日に食べる年越しそばは、江戸時代から、庶民の間に定着したのではないかといわれています。年越しそばを食べ始めた由来には、いくつか説が伝わっており、はっきりとしていません。ですが、年末年始の買い物に出かけると、たくさんのそばを見かけるように、年越しそばは現在まで続く、年末の風物詩となっています。
売られているそばを見ると、生めんや乾めんなどさまざまです。また、かけそばとざるそばのどちらにするのか、トッピングを何にするのかなど、いろいろな食べ方がされています。京都では、にしんの甘露煮をかけそばにのせた「にしんそば」が有名で、京都の年越しでは、にしんそばを食べることも多いようです。
このように、年越しそばの食べ方に決まりはありません。なぜ、大晦日に年越しそばを食べるようになったのでしょうか。意味と由来を探っていきましょう。
なぜ大晦日に食べる? 年越しそばの意味
年越しそばの由来はさまざまですが、どれも縁起や験を担いだ理由が伝わっています。大晦日に年越しそばを食べることで、1年間にあった災難や厄を落とし、新しい年を迎えるのです。
なぜ、めん類の中で、そばが大晦日に食べられるようになったのでしょうか。
もともと、江戸時代には、行事や節目にそばを食べる習慣があったそうです。その習慣の一つが「晦日そば(みそかそば)」です。
江戸の商人は、働いた奉公人をねぎらうために毎月月末にそばを食べていました。大晦日にそばを食べるようになったのも、晦日そばの習慣が関わっているといわれています。
現在は全国に広まっている年越しそばですが、香川県の一部地域ではうどんを食べるなど、地域によって習慣が違うこともあります。
古くから伝わる日本の風物詩! 年越しそばの由来
諸説ある年越しそばの由来の中で、有力なものは5つです。どのような由来で食べられ始めたのでしょうか。
1つ目は、「長寿祈願のため」です。そばの細長い形状から長寿を祈願して食べられ始めたと考えられています。この説から、年越しそばは「寿命そば」とも呼ばれます。
2つ目は、「運気を高めるため」です。鎌倉時代には、「世直しそば」と称してそば餅がふるまわれたといわれています。食べた人たちは、翌年に運が向いてきたため、大晦日にそばを食べる習慣が始まりました。ここから「運そば」や「福そば」とも呼ばれています。
3つ目は、「厄や災難を切り捨てるため」です。そばは、小麦から作るめん類に比べて切れやすい特徴から、厄や災難を切り捨てると考えられていました。そこから、新年を迎える前に、災厄を落とすために食べられるようになったそうです。年越しそばを別名「縁切りそば」とも呼ぶ由来でもあります。
4つ目は、「健康祈願のため」です。そばは強い植物で、雨や風に強くうたれても、日光を浴びると元気になります。この様子から、健康を願ってそばを食べるようになりました。
5つ目は、「金を集める縁起物のため」です。その昔、金銀細工師が、散らばった金粉を集めるために、そば粉を練ったものを使っていました。そこからそばは、金を集めるという縁起物とされ、大晦日に食べられるようになったそうです。
以上のように、年越しそばにはさまざまな由来があり、どの説も縁起や験担ぎに関わっています。
年越しそばを食べる時間とは
年越しそばの由来を知ると、食べる時間はいつが良いのか気になるかもしれません。実は、年越しそばを食べる時間には、明確な決まりはありません。大晦日のうち、都合の良い時間帯に食べて大丈夫です。
ですが、年越しそばは厄や災難を落とす意味があるため、年をまたいで食べることは避けたほうが良いといわれています。
食べる時間は家庭によってさまざまですが、夕飯や夕飯後の夜食として食べることが多いようです。こだわりのそばを用意したり、そば店を訪れたりして、年越しそばの由来を思い返しながら食べるのも良いかもしれません。
年越しそばを食べるタイミングについては、「年越しそばはいつ食べる? 地域によって異なる食べるタイミングを徹底解説!」をご覧ください。
お取り寄せ・通販できる年越しそばランキング
そば粉100%の十割蕎麦、ご当地素材を使う蕎麦など、全国各地の美味しい「お取り寄せ蕎麦ランキング」をご紹介します。





























 取り寄せたい
取り寄せたい 贈りたい
贈りたい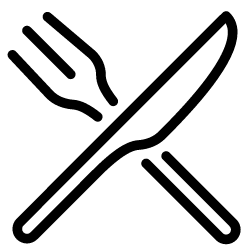 おいしく食べたい
おいしく食べたい 行ってみたい
行ってみたい 食のプロ連載・特集一覧
食のプロ連載・特集一覧



